 |
 へび座 M16 わし星雲 距離 5500光年 へび座とたて座いて座の境界にある散光星雲 へび座 M16 わし星雲 距離 5500光年 へび座とたて座いて座の境界にある散光星雲
撮影2018年7月15日 岐阜県 チャオ御嶽にて撮影
BRC250 1258㎜ f5.1 カメラ SBIG STL11000 冷却モノクロカメラ -22度
L15分X4枚 RGB(red green blue)2X2ビニング Astrodon Iタイプフィルター Stella image8
とPhotoshop-CC処理 flat dark演算
|
 |
 ヘルクレス座M13 球状星団 2018年5月19日 長野県上村で撮像 ヘルクレス座M13 球状星団 2018年5月19日 長野県上村で撮像
距離 2万5100光年 満月の3分の1ほどの大きさを持ち、
50万個もの星が含まれる大集団 RC250M 1268㎜ f5.1カメラ
SBIG STL11000冷却モノクロカメラ -35℃ L15分露光 L画像4フレーム 1分+15分
RGB2X2ビニング10分 各2枚 合成 ダーク演算 フラット補正
|
 |
オリオン座 モンキーフェース星雲 2013年撮像 山梨県北杜市 瑞牆山にて オリオン座6400光年 BRC250M 1268㎜ f5.1カメラ SBIG STL11000冷却モノクロカメラ フィルター L15分露光
L画像4フレーム 10分4フレーム -35℃ RGB2X2ビニング10分 各2枚 合成 ダーク演算 フラット補正
|
 |
一角獣座 わし星雲 赤経 07h05 赤緯 -10゚42'視直径 85'×25' 距離 1820光年写真では、赤く染まった雲が翼を広げて空を飛ぶわしの姿になっているので、わし星雲という愛称がついている。英語の愛称である「Seagull」とは「かもめ」のことである撮像場所:長野県飯田市 上村2013年12月7日鏡筒高橋製 BRC250M 1268㎜ f5.1カメラSBIG STL11000冷却CCDモノクロカメラ‐35℃ フィルターAstrodon Iタイプ L画像15分 4枚 RED×2枚 Green×2枚 Blue×2枚(2X2 )ビニング 合計露光120分Stellaimage7 photoshop Cs4 処理
|
 |
一角獣座 バラ星雲 撮影2012年10月14日 長野県 大滝村気温0度SBIG STL11000 M 高橋製作所 BRC250 焦点距離1268mm F5.1 PhotoShop CS4と Stella image6にて 処理 M 15分露光 L画像4フレーム-35℃ RGB2X2ビニング10分 各2枚 合成 ダーク演算 フラット補正 RGB フィルター アストロドンIタイプ |
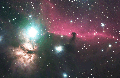 |
オリオン座 馬頭星雲 撮影2012年9月15日 長野県 大滝村気温0度SBIG STL11000 M 高橋製作所 BRC250 焦点距離1268mm F5.1 PhotoShop CS4と Stella image6にて 処理 M 15分露光 L画像4フレーム-25℃ RGB2X2ビニング10分 各2枚 合成 ダーク演算 フラット補正 RGB フィルター アストロドンIタイプ |
 |
M45 プレアデス星団 (スバル)2011年12月24日 撮影場所:静岡県 天城高原 気温‐5度 SBIG STL11000 M 高橋製作所 BRC250 焦点距離1268mm F5.1 PhotoShop CS4と Stella image6にて 処理 M 15分露光 L画像8フレーム-35℃ RGB2X2ビニング10分 各2枚 合成 ダーク演算 フラット補正 RGB フィルター アストロドンIタイプ |
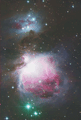 |
M42オリオン大星雲 2011年12月24日 赤経 05h35m.4 赤緯 -05゚27 実視等級 4.0等 視直径 66'×60' 距離 1500光年撮影場所:静岡県天城高原 気温‐5度 SBIG STL11000 M 高橋製作所 BRC250 焦点距離1268mm F5.1 PhotoShop CS4と Stella image6にて 処理
L 15分露光 L画像4フレーム 1分3フレーム -35℃ RGB2X2ビニング10分 各2枚 合成 ダーク演算 フラット補正 RGB フィルター アストロドンIタイプ |
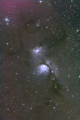 |
M78 赤経 05h46m.7 赤緯 +00゚03'
実視等級 8.3等 視直径 8'×6' 距離 1600光年
2011年11月26日 撮影:長野県 飯田市 上村 SBIG STL11000 M 高橋製作所 BRC250 焦点距離1268mm F5.1 PhotoShop CS4と Stella image6にて 処理 M 15分露光 L画像8フレーム-35℃ フィルター アストロドンIタイプ RGB2X2ビニング10分 各2枚 合成 ダーク演算 フラット補正: オリオン座 三つ星の北東にある星雲 ウルトラマンの生まれた星で有名な星雲です |
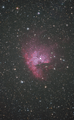 |
カシオペヤ座 NGC281 NGC281 散光星雲
光度: 7.0等 視直径:35.0' 赤経:00h49m51.9s 赤緯:+56゚20'43" (B1950)
赤経:00h53m32.4s 赤緯:+56゚41'16" (視位置) カシオペヤ) シェダル付近の散光星雲 2011年11月26日 長野県 飯田市 上村にて撮影 高橋製作所 BRC250 焦点距離1268mm F5.1 PhotoShop CS4とStella image6にて 処理 使用カメラ SBIG STL11000
M 15分露光 L画像4フレーム-35℃フィルター アストロドンIタイプ RGB2X2ビニング10分 各2枚 合成 ダーク演算 フラット補正 |
 |
M8 射手座の干潟星雲赤経18h03.8 赤緯-24°23′実視等級 6.0等 視直径 60'×35' 距離 3900光年
撮影場所: 長野県飯田市上村 カメラ Cannon EOS-5D DIGITAL IDAS AP改造
高橋製作所 BRC250焦点距離1268mm F5.1
ISO800 7枚撮影した画像をPCにてPhotoShop-CS4とステライメージ6で合成処理
夏の星雲の代表ともいえるとても美しい散光星雲。肉眼でもその位置はすぐわかる。「干潟星雲」という名前は、大きな星雲の中を横切る暗黒帯の複雑な模様が、写真では水が引いたあとの干潟のように見えることから名づけられたもの。NGC
6530という明るい散開星団が重なっているので、とてもにぎやかで、すばらしい眺めを楽しめる。 |
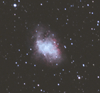 |
M1 おうし座の超新星残骸 かに星雲 2010.年12月5日 実視等級 8.4等 視直径 6'×4' 距離 7200光年 撮影場所:長野県 飯田市上村 高橋製作所 BRC250 焦点距離1268mm F5.1 PhotoShop CS4 ステライメージ6 処理 ダーク演算 フラット補正 使用カメラ CannonEOS5D IDAS AP改造 ISO800 18分露光 8フレーム合成
123ζ Tau(おうし座)角に当たる部分に在る 星雲 大望遠鏡ではその構造(フィラメント構造が、がカニの足のように見えることから かに星雲と付けられた。 |
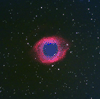 |
NGC7293みずかめ座 惑星状星雲 2009年9月21日 気温5度 長野県 大滝村で撮像 赤経 22h29m.6 赤緯 -20゚48'実視等級 7.0等 視直径 15' 距離 490光年 高橋製作所 BRC250 焦点距離1268mm F5.1 PhotoShop CS2 処理 使用カメラ CannonEOS5D IDAS AP改造 ISO800 15分露光 4フレーム合成 みずがめ座にある惑星状星雲。大きさは満月の2分の1程度にもあり、見かけの大きさが最大の惑星状星雲である。以前25年位前に乗鞍の畳平で20cmの経緯台付きの反射望遠鏡で見せて頂いた際 らせん状に見えた記憶が有ります 現在は中々このような空に会えなくなりました。 |
 |
バラ星雲散光星雲 2009年9月21日長野県 大滝村で撮像 気温5度 赤経 06h30m.3 赤緯 +05゚03 実視等級 6.0等 視直径 60' 距離 4600光年 高橋製作所 BRC250 焦点距離1268mm F5.1 PhotoShop CS2 処理 使用カメラ CannonEOS5D IDAS AP改造 ISO800 15分露光 4フレーム合成 いっかくじゅう座の散光星雲。実際には、NGC
2237~39、NGC 2246の4個の星雲・星団が集まったもので、見かけの大きさは満月の2倍ほど。写真で撮影すると、ばらの花のような赤い星雲の姿が浮かび上がるので、この愛称がある。ばらの花びらの部分には、入り組んだ暗黒星雲のすじや暗黒物質の黒い点などが分布しているのがわかる。この黒点はグロビュール(胞子)と呼ばれ、ガスやダストが収縮しつつある星形成段階にある。星雲の中央にはまるでばらの花粉のような散開星団NGC
2244が美しい。双眼鏡だと散開星団NGC 2244はとらえられるが、散光星雲の方は淡いので、双眼鏡や望遠鏡を用いてもたいへん見づらい。 |
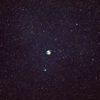 |
M27(あれい状星雲)2002年10月5日 BRC250、f5,1 1268mm 反射望遠鏡の直接焦点にて撮影 使用カメラは光映舎アストロカメラ ボディー、6×9 フィルムはKodakポートラ800露出30分 こぎつね座にある 最も美しい惑星状星雲で この星雲は、カラフルな色が好きです 光映舎 アストロカメラ6×9 撮影地は岐阜県 大野郡 丹生川村 乗鞍岳 大雪渓 今年が最後のマイカー乗り入れで残念です 未発表作品 |
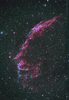 |
網状星雲 2008年11月01日 撮影場所:長野県 飯田市上村。高橋製作所 BRC250 焦点距離1268mm F5.1 PhotoShop CS2 ステライメージ5にて,7分露光の画像 4枚合成 IDAS APカメラ改造 ISO1600
はくちょう座にある超新星残骸。広い範囲に分布している星雲(NGC 6960、6992-5)をまとめて、この名前がついている。約7万年前に爆発した超新星の残骸と考えられる。たいへん淡いので小さな望遠鏡では確認しづらいが、写真ではレースのような美しい姿を見ることができる。赤経
20h45m.7 赤緯 +30゚43'(NGC 6960) / 赤経
20h56m.4 赤緯 +31゚43'(NGC 6962)実視等級 8.0等(NGC 6962) 視直径 150' 距離 1600光年 |
 |
スバルM45(おうし座)プレアデス星団 2007年12月1日 赤経 03:47:.1 赤緯 24゚06'実視等級 1.6等 視直径 120' 距離 440光年BRC250、f5,1 1268mm
反射望遠鏡の直接焦点にておうし座の左肩のあたりに肉眼でも見え、都会地でも位置はわかる。観望には双眼鏡が最適で、7倍×50ミリメートルの双眼鏡では、明るい星の配列が、小型のひしゃく、あるいは羽子板を連想させ、見事な姿を楽しめる。EOS-5DIGITAL 15分×4枚 PCにて合成ステラナビゲーター5 PhotoShop
CS2にて画像処理 撮影場所:長野県 飯田市 しらびそ高原にて撮影 |
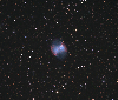 |
M27(あれい状星雲)2005年5月4日BRC250、f5,1 1268mm 反射望遠鏡の直接焦点にて撮影 使用カメラはCannon EOS KISS DIGITAL ボディー露出711秒×4枚 COMPOSITE 合成 Photoshop CS2 RAP ステライメージ4で画像処理 上の銀塩写真と比較し解像度の高い事が分かります。撮影地は長野県 下伊那郡 上村にて撮像 未発表作品 |
 |
網状星雲2001.4.28 BRC250、f5,1 1268mm 反射望遠鏡の直接焦点にて撮影 使用カメラは光映舎アストロカメラ ボディー、6×9 フィルムはコダックE100S・(120)ブローニー はくちょう座の翼にある星雲です フィルムは、Kodakポートラ800 露出は30分 撮影場所は長野県下伊那郡上村 しらびそ高原にて未発表作品 |
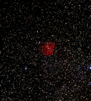 |
モンキー星雲2000年12月31日口径20cmε式反射望遠鏡の直接焦点にて撮影f4. 使用カメラはマミヤプレスホルダⅢ67ボディー、フィルムはコダックE100VS・(120)ブローニー標準現像75分露光 オリオン座にある散光星雲 オリオン座にある散光星雲で、よく見るとサルの横顔に見えることからこの名前が付けられた。双子座の足元にある星雲です、2000年は異常気象で新月になると殆ど晴れず、最後の最後やっと晴れてくれました。撮影地は長野県下伊那郡しらびそ高原。未発表作品。 |
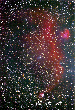 |
わし星雲2002年10月13日、BRC250、f5,1 1268mm 反射望遠鏡の直接焦点にて撮影 使用カメラは光映舎アストロカメラ ボディー、6×9 フィルムはコダックE100S・(120)ブローニー
80分露光・2倍増感。わし星雲は視直径85′×25′距離1800光年・いっかくじゅう座にある散光星雲IC2177のこと。おおいぬ座との境にあります。写真では、赤く染まった雲が翼を広げて空を飛んでいるような姿になっているので、わし星雲という愛称が付いている。・・撮影地は乗鞍 大雪渓。未発表作品 |
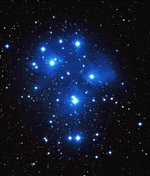 |
M45(スバル)1997年11月2日、口径20cmε式反射望遠鏡の直接焦点にて撮影f4.
使用カメラはマミヤプレスホルダⅢ67ボディー、フィルムは
フジカラーアスティア100・(120)
90分露光・4倍増感。M45は、牡牛座にあり、自動車の名前スバル、や別名プレアデス星団と言い、130個の散開星団で、若い星です・・撮影地は長野県下伊那郡しらびそ高原。未発表作品。 |
 |
ペルセウス座2重星団1999年10月11日、高橋製作所ε200にて撮影f4使用カメラは、マミヤプレスフォルダーⅢフィルムは、Kodak
E100VS・(120)30分露光・。ペルセウス座は、カシオペヤ座の隣の星座で、カラーで撮影すると色々カラフルな星雲などが見えます、星団が二つ重なっているので2重星団と呼んでいます、・撮影地は乗鞍岳畳平。未発表作品。 |
 |
M46,471997年1月3日、口径20cmε200の直接焦点にて撮影f4.
使用カメラはマミヤプレスホルダⅢボディー、フィルムは
フジカラースーパーG400・(120) 30分露光・。シリウスの東を流れる淡い冬の天の川の中にある、肉眼でも見える明るく美しい散開星団。M47はメシエの記録した場所に存在せず、M46の少し先の明るい星団ということで同定された。どちらも双眼鏡でたいへん美しい。、・撮影地は撮影地は静岡県、熱川。未発表作品。 |
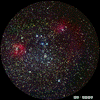 |
IC410.IC4052000年12月31日高橋製作所ε200の直焦点800mm-f4マミヤプレスホルダーⅢフィルムKodakE100Sブローニー(120)+2増感現像。露出75分露光。ぎょしゃ座にある散光星雲右側の星雲はマガタマ星雲とも呼ばれています。透明度があまり良く無かったので、撮影地はしらびそ高原。未発表作品。 |
 |
まゆ星雲IC51461999年11月7日。別名コクーン星雲光度7.2等1999.11.14口径20cm高橋SSε200の直焦点にて撮影f-4×800mm。カメラマミヤプレスホルダーⅢボディー、フィルムKodakE100S露光75分現像+2増感はくちょう座にある星雲で、直ぐ側には、とかげ座があり
天の川の中にひっそり小さいが写真で確認できる撮影地は長野県下伊那郡しらびそ高原。未発表作品。 |
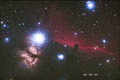 |
オリオン座 馬頭星雲 2010年12月5日 長野県 飯田市 上村撮影 高橋製作所 BRC250 焦点距離1268mm F5.1 PhotoShop CS4 処理 使用カメラ CannonEOS5D IDAS AP改造 ISO800 18分露光 8フレーム合成 ダーク演算 フラット補正
冬場は、中々シーンチレーションが悪く 星像がシャ-プに撮れませんが、この日は、比較的にシーイングが良く、風も少なく撮影できました
気温2度 もう少し温度が下がってくれるとノイズが少なく良かったのですが・・・ |
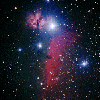 |
馬頭星雲1997年1月3日、口径20cmε式反射望遠鏡の直接焦点にて撮影。標準現像 使用カメラはマミヤプレスホルダ、フィルムは
フジSuperG400(120) 30分露光×2ネガ2枚重ね。撮影地は静岡県、熱川、標高700m。
体が動く強風で、微恒星が膨らみました。しかし透明度は、良かったようでカラフルに写りました、未発表作品。 |
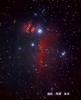 |
馬頭星雲 赤経 05h41.0m 赤緯 -02゚24'
視直径 60' 距離 1100光年(理科年表2002)2003年12月28日、BRC250、f5,1 1268mm 反射望遠鏡の直接焦点にて撮影。使用カメラは光映舎アストロカメラ ボディー、6×9 フィルムはコダックE100S・(120)ブローニー
60分露光・2倍増感。撮影地は静岡県、天城高原標高1000m。オリオン座にある散光星雲IC434の東側に浮かび上がる、馬の首の形にそっくりの暗黒星雲のこと。口径の大きな望遠鏡を使えば、散光星雲を背景にした影絵のようなイメージで見える。暗黒星雲中では、活発な星形成が行なわれている。 、未発表作品。 |
 |
カリフォルニア星雲1997年1月3日、口径20cmε式反射望遠鏡の直接焦点にて撮影。標準現像
使用カメラはマミヤプレスホルダ、フィルムは
フジSuperG400(120)
30分露光×2ネガ2枚重ね。撮影地は静岡県、熱川、標高700m。
この日は、馬頭星雲を撮った翌日の夜で、透明度は、前日のほうが、少し良かったのですが、シーイングが良くシャープに撮れました。未発表作品。 |
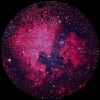 |
北アメリカ、ペリカン星雲1998年8月23日、口径20cmε200f4反射望遠鏡にて撮影。
使用カメラはマミヤプレスホルダーⅢ型、フィルムは
コダックエクタクロームE200(120)1時間露光、4倍増感現像、天の川が、とても素晴らしくこの日の乗鞍は、透明度が、素晴らしく、撮影できて楽しかったです。撮影地は乗鞍。 |
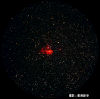 |
M17(オメガ星雲)1997年11月3日、口径20cmε式反射望遠鏡の直接焦点にて撮影f4.
使用カメラはマミヤプレスホルダⅢ67ボディー、フィルムはコダックE100S・(120)ブローニー
90分露光・4倍増感。カシオペア座のシェダルと言う星の近くにある散光星雲で、望遠鏡では見えませんが、写真に撮ると真っ赤な星雲が浮かび上がります。・・撮影地は長野県下伊那郡しらびそ高原。未発表作品。 |
 |
M42オリオン大星雲1995年9月4日、口径20cmε式反射望遠鏡の直接焦点にて撮影。標準現像
使用カメラはマミヤプレスホルダ、フィルムは
フジSuperG400(120)
40分露光。撮影地は岐阜県乗鞍岳畳平。月刊天文ガイド入選。 |
 |
M8,20干潟、三裂星雲1998年8月23日、口径20cmε式反射望遠鏡の直接焦点にて撮影f4.
使用カメラはマミヤプレスホルダⅢ67ボディー、フィルムはコダックPPF・(120)ブローニー夏を代表する大型の散光星雲M8干潟星雲、M20三裂星雲ともに、射手座にあります、望遠鏡で見てもその存在はわかりますが、残念ながら、カラーでは、見えません
撮影地は岐阜県乗鞍。未発表作品。 |
 |
三烈星雲M20 2005年5月4日 711秒 ×2枚PCにて合成 Cannon EOS KISS DIGITAL CAMERAにて撮影地 長野県 下伊那郡 上村 いて座の干潟星雲M8のすぐ北にあり、三裂星雲の呼び名で親しまれている散光星雲。明るい散光星雲が暗黒星雲によって3つに引き裂かれたように見えるので、ジョン・ハーシェルによって命名された。星雲中にあるO7型の7等級の高温星の放つ光によって照らし出されているもので、本体は淡いピンク色をしているが、すぐ北に青い色をした散光星雲が隣接していて、20cm以上では見事なコントラストを見せてくれる。写真ではよりいっそうすばらしい。未発表作品 |
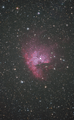 |
NGC2811997年11月3日、口径20cmε式反射望遠鏡の直接焦点にて撮影f4.
使用カメラはマミヤプレスホルダⅢ67ボディー、フィルムはコダックE100S・(120)ブローニー
90分露光・4倍増感。カシオペア座のシェダルと言う星の近くにある散光星雲で、望遠鏡では見えませんが、写真に撮ると真っ赤な星雲が浮かび上がります。・・撮影地は長野県下伊那郡しらびそ高原。未発表作品。 |
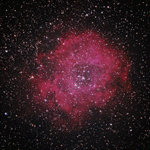 |
ばら星雲1993年11月15日、口径20cmε式反射望遠鏡の直接焦点にて撮影f4.
使用カメラはマミヤプレスホルダ、フィルムは
フジSHG400(120)オリオン座の左にある星座で、いっかくじゅう座にある、この星雲は、バラの花びらに見える事から、この名前が付けられました。
20分露光のネガを2枚重ねてプリント。撮影地は
富士山新五合目。月刊天文の表紙に掲載。 |
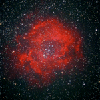 |
バラ星雲2002年10月13日 高橋BRC250 1268mm f5.1反射望遠鏡で撮影光映舎6×9アストロカメラ FM60すりガラスによるピンと合わせ フィルムは、KodakE100S 70分露光 プラス1増感現像 この日を最後に乗鞍エコーライン スイカイラインがマイカー規制となる。長野県乗鞍大雪渓駐車場にて、月刊天文ガイドに掲載 |

